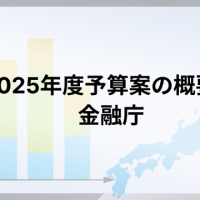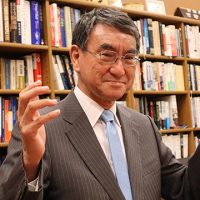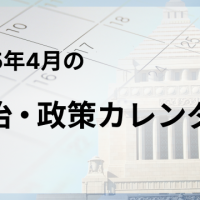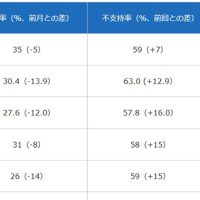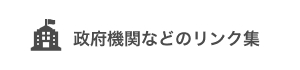財政法は戦後80年続くGHQの呪縛
「国債増で破綻」は誤り、信用創造・積極出動で説く日本経済の処方箋
財政政策で積極的出動と健全化のいずれを重視するかは、交わらない「神学論争」に映る。経済が「失われた30年」と呼ばれる日本では、昨今の物価高騰と相まって、減税や教育関連の無償化など負担軽減の議論が熱を帯びる。国債発行の意義を前向きにとらえ、積極財政派の論客として改めて注目を浴びるのが税理士でもある西田昌司参院議員(自民党、京都選挙区)だ。
会計学の視点を交え、理詰めで閣僚らから答弁を引き出すやり取りは、国会質疑の見どころの定番と言っていい。丹念に事実を示しながら「常識」に挑む言説は、脈々と続く戦後財政の「呪縛」にも及んだ。

西田昌司参院議員の発言のポイント
・政府はインフラ開発などの長期計画を示し民間の投資意欲を促すべきだ
・現在の日本経済は政府による積極的財政出動が不可欠
・「国債残高が増えれば財政破綻」との考えは誤り
・占領下にできた財政法は日本政府の財政自主権を制約する狙いがあった
・「年収の壁」引き上げは個人消費拡大に効果
・プライマリー・バランスではなく物価上昇率や投資額に着目すべきだ
・無から有を生み出す「信用創造」の理解が大切
※聞き手:政策ニュース編集部
インタビューは2025年2月5日に実施しました
「国債は子や孫にツケ」は本当か
― 日本経済の現状をどのように見ているか。
(西田昌司氏、以下同じ)まず、停滞の原因をしっかり見極めることが重要だ。政府はこの30年間、必要な財政出動をしなかった。 以前は長期的インフラ整備を「総合開発計画」に沿って毎年実行し、公共事業関係費は現在の3倍の年15兆円ほどあった。補正予算を足して総額約20兆円になった年もある。長期計画があれば、地方自治体も民間企業もそれに合わせ、地域でさまざまな投資をする。
ところがその計画がなくなった上、公共事業関係費もこの30年間で一挙に減った。民間投資額は激減し、民間部門は「貯蓄超過」に陥っている。借り入れや投資をするより貯蓄しているわけだ。国民総生産(GDP)は低迷し、税収が減った。税収不足を補うため発行した赤字国債は現在で累積1000兆円を超すが、それは投資ではなく民間部門で貯蓄に回っている。だから経済成長していない。
― 国債残高が増えている。
それでどうなったかというと、一つは政府が国債を出し渋るようになった。「国債残高を増やすと財政破綻する」という間違った理論を真実だと思い込み、「孫や子の代まで税金で国債を償還することになり、国家財政が大変なことになる」と言ってきた。しかし30年経って既に孫や子の代なのに財政破綻していない。理由は、国債償還はすべて借り換え債を発行し、それに差し替えているだけだからだ。政府が国債を発行して財政出動し、結果的に民間の貯蓄を増やし、その償還は借り換え債で行っている。こうした流れなので破綻のしようがない。
問題は、政府が長期計画による財政出動をしなくなり、民間が積極的に投資する気力と機会を失くした点にある。破綻したのは財政でなく国民経済だ。新たな投資がないため地方で人が暮らせなくなり、人口減少の要因ともなった。
1月の利上げ決定は愚策
― 民間企業の投資意欲を減退させてしまったと。
もう一つ原因がある。1988年にBIS規制が策定され、国際業務に携わる銀行の自己資本比率規制を、それまでの4%以上から8%以上に引き上げた。これで貸し出せる額が半分になった。その数年後に日本でこの規制が本格適用され、これによって、600兆円あった金融機関の融資残高は、「不良債権処理」の名目の下で400兆円台に落ち込んだ。つまり3分の1のお金(約200兆円)が消えた。とんでもないことをしたわけだ。それに懲りて民間企業は投資のために借り入れることがトラウマになった。民間で融資や投資が落ち込んだのなら、政府が国債発行してどんどん景気対策すれば良かったのだが、約200兆円もの金額が一気に消えたため、10兆~20兆円の経済対策では焼け石に水だった。民間企業は負債を減らし、身の丈に合わせた経営をせざるを得なくなった。
同時に、政府では「国債発行して財政を悪化させてはいけない」という間違った暴論が「正論」になり、今日まで続いている。民間も政府も投資しなくなり「デフレ社会」が出来上がった。財政再建論者はこうした現実をまったく見ていない。 財政再建自体に意味はなく、必要なのは国民経済の再生だ。
― どうすればいいのか。
これまでの逆をすることだ。政府が長期計画を示して毎年、当初予算で相当のインフラ整備、更新を計上すれば、民間企業は投資額を増やし、経済が上向いてくる。やがてインフレ率が2%を超えて、3~4%に過熱してくれば金利を引き上げて調整すればいい。しかし、民間と政府の投資額が増えていないのに日銀は今年1月、0.25%の利上げを決めた。やるべきこととは正反対の愚策である。インフレ率が3%を超えたと言っているが、それは需要増による「デマンドプルインフレ」ではなく、輸入品の価格上昇などに起因する「コストプッシュインフレ」、つまり悪いインフレだ。
日銀は「市場との対話」と言うが、市場とはつまり銀行のこと。銀行は金利を下げているのに投資額が増えておらず、収益が上がらない。よって利上げを望んでおり、それに応えたのが「市場との対話」の実情だ。今回0.25%引き上げた結果、メガバンク全体で3000億円の増収になると新聞に出ていたが、まさに銀行のためにやっている。もう一つの大きな意味は、金利が上がると、予算の一般会計から出る国債の利払い費が増えることだ。国債残高が1000兆円なら、0.25%利上げすると2.5兆円の増加。これは「国債の利払い費が増えるので、国債残高を増やしてはならない」という財務省の論法を日銀が後押ししていることになる。利上げの背景には、こうした財務省への「気遣い」がある。
日銀に支払った国債の利息は政府に戻る
― 国債の利払い費が上がっても政府は困らないのか。
実は日銀に利息を支払っても、法律上は経費を引いた後で「日銀納付金」として政府に戻ってくる仕組みになっている。現在は国債残高の半分を日銀が持っており、利払い費の半分は日銀に行って政府に返ってくるので、負担は極端には増えない。これは私が国会質問で政府答弁として引き出している。やるべきことは民間が投資を増やせる環境づくりであり、金利は低いままの方がいい。政府が今後、何に予算を投じ、どういう分野に補助を出すかなどを具体的に毎年示せば、間違いなく民間はそれに合わせて投資する。しかし、その第一歩である財政出動自体が止まっている。
理由は、プライマリー・バランス(PB)の黒字化というまったく無意味なことに執着しているためだ。政府はPB黒字化を目標値として十分に財政出動せず「失われた30年」を招いた。こうした事実に政府が気付いていなかった節がある。さらに、占領中の1947年(昭和22年)にできた「財政法」が財政拡大を否定する内容であることも大きな原因だ。戦費調達のための国債大量発行で市中のお金が増えすぎ、戦後に激しいインフレになり、これを抑えるために財政法を作ったと一般的には言われている。しかし、実はこれもでたらめなのだ。
「欲しがりません勝つまでは」は秀才官僚のインフレ抑制策
― 戦後すぐの話までさかのぼる必要があると。
戦時中はこのような法律はなかったが、実は大きなインフレは起きていない。当時は供給力のほとんどを戦争遂行に回しており、大量に国債を発行して軍需物資を買い、それによって国民の側に多額のお金が渡っていた。ただ、国民がそのお金を自由に使うと大変な供給力不足に陥りインフレは不可避となる。よって「お金は渡すけれども、手に入れたからといって使ってはならない」という理屈を「欲しがりません勝つまでは」の標語にして浸透させ、統制した。つまり、当時の大蔵官僚は大変な秀才だったわけだ。
戦後はその統制が外れ、国民がそれまで我慢してきた分、欲しいものに使い出して供給力不足となり、需要と供給のバランスが崩れた。また、終戦直前は国土の至る所が空襲で焼かれ、供給力が極端に落ちていた。それで戦後の大インフレとなったのだが、原因は国債発行ではなく、著しい需給バランスの崩壊だった。
― なぜ財政法が作られたのか。
財政法には、さらに別の狙いがあった。それは財政健全化を建前として、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府から財政自主権を取り上げることだった。占領中に政府が勝手なことをしないよう、歳出に厳しい制約を設けたということだ。例えば、再び戦争を起こさせないようにするため、まずは新憲法で不戦の誓いを立てさせ、財政法で歳出を縛って戦費を調達できなくした。これでは戦争をしようにもできない。このように歳出を制限すれば、ほかのことでも政府は自由な政策ができなくなるわけだ。しかし、そういう真の目的は国民に教えたくないので、GHQは「財政健全化」だけを言った。国民は、そのまま今まで信じてきた。
ここまで言うと真実が見えてくる。本来は、災害が起きたり、新型コロナウイルスのような感染症が大流行したりすれば、多額の財政出動が必要だ。ところが、これまで終戦直後の状況を前提とした政策を延々と続けてしまった。政府は特にこの30年間、財政法を盾に厳しい歳出管理を徹底した。
プライマリー・バランスは単なる結果論
― 年収の壁の引き上げが焦点となっている。
年収の壁の引き上げは、178万円までがふさわしいかどうかはともかく、行うべきだ。経済では国民の個人消費が最も大きく、それを拡大するには手取りを増やさねばならない。給料アップは大事だが、減税でも手取りは増える。仮に178万円に引き上げると8兆円ぐらい財源が必要だと言われているが、それは国債で賄えばよい。毎年、全体で手取りが8兆円増えれば消費が拡大し、取引や所得の増加につながり、税収増となる。
予算の財源は税でなくとも通貨発行、つまり国債で全部できる。そして国債発行により財政出動したお金を税金として回収するわけだ。これを1年間トータルで見ると、歳出と税収が同じくらいになる場合もあるし、税収が歳出を上回る年もあれば、歳出が多くて税収が少ないこともある。経済状況により変わるだけだ。こう考えるとPBが黒字か赤字かは単なる結果論にすぎない。何の意味もないことに30年も固執している。
― 政策は財源とセットで議論されることが多い。
財源を先に論じるのではなく、指標として物価上昇率や投資額に注目するのが正しい。それらが大きくなる方向で進むことが必要だ。そして拡大しすぎたと判断したら、財政破綻を懸念するのではなく、経済が極端にインフレになることを防ぐために金利や税率を引き上げたり、予算執行額を減らしたり、さまざまに調整できる。
高名学者もミスリード
― 政府の財政政策が根本的に変わらない理由は。
一つは単純な間違いだ。知らなかったり勘違いしていたりというのもあると思う。しかし、何十年も大間違いをしておいて、誤りだと分かっても今さら直せないというのは断じて容認できない。もっとも、政治家も間違っていたのであり、財務省だけを責めてもかわいそうだ。私自身も誤りに気付いていなかったが、「何かおかしい」と思い調べていくと事実が分かり、十数年前から今のような主張を始めた。ただ、そういう事実や理論、考え方を教えている所はなかったので、気付かなくても仕方ない。
そもそも大学や研究者も「予算は税収の範囲内でつくるべきだ」と信じ込み、経済の実態やお金が回る本当の仕組みを正しく教えていなかった。それどころか「国債による財政拡大は無責任」といった言説は現在もあふれている。財務省の顧問的な立場で発言している著名な学者の話などを聞いても「いったい何を言っているのか」と首をかしげることがある。
― 「常識」が誤りだったということか。
例えば「銀行はどうやってお金を貸すのか」という経済の基本事項について、高名な大学教授でも間違った記述をしていることがある。「銀行は、皆さんが預けた預金を元にお金を貸し出している」と書いている。有名な先生の教科書なので、みんなそう思い込んでいるが、事実は逆だ。銀行は預金を集めてから、それを貸し出しに回すのではない。返済能力のある借り手から借用証書を取り、預金通帳に貸出額を記入するだけで、貸し出しを行っている。預かったお金の何倍もの額を、通帳記入だけで融資しているわけだ。これが「信用創造」。
そして、政府による国債発行も同様に信用創造だ。政府が国債を発行し、それで得た資金を予算として公共事業・サービスなどで執行すれば、そのお金は民間側の預貯金に回る。民間つまり国民は、その預貯金で物を買ったり、サービスを受けたりする。まとめると、国民の預貯金が増えるのは、銀行から借り入れしたときか、政府が国債を発行したときとなる。大切なのは、信用創造は最初から相当の財源がなければできないわけではなく、財源の制限を受けない「無から有を生み出す道具」と言えるわけだ。
「火あぶり」になっても地動説
― もう少し詳しく。
学者や官僚はよく「民間に国債を買ってもらうと国民の預貯金を減らすので、景気が上向いて民間側が進んでお金を使おうとしても、出回っているお金の量が減っているから金利が上がって経済に悪影響を与える。よって財政出動や公共事業はそれほど効果がない」という説明をする。こういう誤りは「国民の預貯金から貸し出すので、結果的に金利を上昇させる」という前提で考えることから生じる。信用創造とは「何もないところから負債と資産が出てくる仕組み」ということを理解していない。
また、民間企業であれば借入金は銀行に返済せねばならないのに対し、政府の借入金である国債は償還期限が来ると、新たに「借り換え債」を発行して差し替えるだけであり、事実上返済していない。さらに先に述べた通り、国債残高の半分を日銀が保有しているため、利払い費の半分は政府に戻って来ている。財政破綻のしようがない。
― 財政政策の転換はあり得るのか。
政府はこうした事実に目を向けず、誤った政策に固執している。しかし、例えて言うと、最初は太陽が地球の周りを回っているとする「天動説」が唱えられていたが、地球が太陽の周りを回る「地動説」が正しいと改めた「コペルニクスの転換」の歴史がある。地動説に変わるまで何百年かかったことも、日本の状況とよく似ている。忘れてはならないのは、地動説を主張していた人は、それが認められるまで迫害され、大量に火あぶりで処刑されていったことだ。これも今のわが国のようだ。
国民の血税を大切に使うモラルは必要だが、科学的事実と倫理は分けて考えなければならない。本当の優秀さとは、教科書を理解する頭脳だけではなく、同時に現実を見て自分で解決策を考え出せることだ。政治家や官僚、学者は自分が教わった学説を一方的に信じているだけではいけない。
関連リンク
・西田昌司 – 経歴、関連ニュース、公式サイトへのリンクなど。自民党