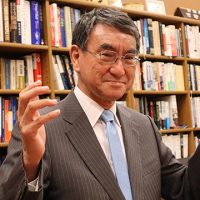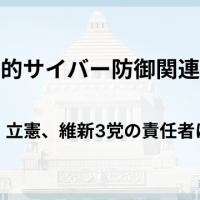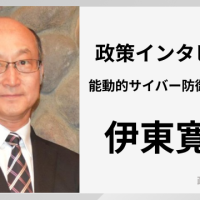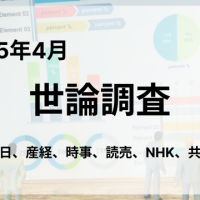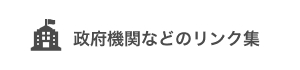通信の秘密も人権、安全で平穏な生活も人権
― 日本国憲法の人権規定の「通信の秘密」との兼ね合いをどう考えるか。
(茂田)通信の秘密は大切な人権であり、守らねばならない。しかし、国民には経済的利益もあり、安全で平穏に暮らす権利もある。ある意味で、一番大切な人権というのは、国民が犯罪に遭わずに、安心して安全に暮らすことができ、命が守られるということだ。来日した外国人がよく感激するのは「スマートフォンを置き忘れても盗まれない」「財布を落としても返ってくる」ことだという。国民が豊かに暮らせるのも人権だ。企業の経済的技術情報なども盗まれ放題の国では、経済力は大きく落ちていくだろう。サイバーセキュリティは、直接的には人権とは憲法に書かれてはいないが、国民の豊かに安全平穏に生きる権利につながるものだ。一部の憲法学者が、通信の秘密だけを取り上げて「人権が侵害される」と主張するのは、議論の仕方としてふさわしくないと思う。
米国の連邦裁判所の判決を見ても、片方の人権だけを取り上げるのではなく「通信の秘密」という人権がある一方でナショナルセキュリティもある。これらは相互に対立しているのではなく、ナショナルセキュリティは安全で平穏に生きる人権を守るためにあり、いずれも国民の人権守るためのものだ」という議論の立て方をする。そして「ナショナルセキュリティを通して守られる人権も重要であるので、通信の秘密の範囲は、どこまで譲歩できるか」という双方のバランスを取る議論を真正面からやる。このような考え方が本来あるべき姿だ。乱暴な言い方かもしれないが、国家が崩壊してしまっては、人権もへったくれもないことを、米国はよく分かっている。
― 日本では、どのようなことが必要か。
(茂田)一番大切なことは、米英がやっていること、ワールドスタンダード(世界標準)がどのようなものかを、日本国民が知るということだ。最近はやや色褪せてきたかもしれないが、戦後、日本が憧れてきた民主主義の国である米国でも、実はすごいシギントをやっている。しかし、それは報道されていない。よって日本国民はワールドスタンダードが分からない。私は、一見すると回り道のようだが、世界の国はどのようなシギントをしているのかを日本の報道機関に伝えていただくことが近道だと考えている。ワールドスタンダードを知れば、国民は正しい判断を下してくれると思う。
専門性高い人材育成を
― 今回の法案で、被害を受けた場合に届け出義務を課した事業者の範囲については。
(茂田)最初の法案なので範囲が狭くても仕方がない。ここから始めていくしかないと思う。私が少し気になっているのは、民間企業が出すインシデント・レポートの報告先だ。当該企業の所管官庁や個人情報保護委員会など、いくつも報告するのは大変であり、政府の報告窓口を一つにしてほしいという要請は多いと思う。しかし、この法案は依然、主管官庁が中心だ。もっとも、内閣府にできるNISC(内閣サイバーセキュリティセンター)の後継機関もマンパワーがなく、窓口を一元化しても対応できないかもしれない。また、それぞれの主管官庁にサイバーセキュリティの専門家がいるのかどうかという問題も起きそうだ。UKUSAのうち米国以外はシギント機関にサイバーセキュリティ機関を附置したのは、人材が限られているというのが大きな理由だ。窓口を一本化し、政府としてレベルの高いものを目指す狙いがある。
― 日本政府に専門家は十分なのか。
(茂田)ところが日本は、専門家が足りていない上、その少ない専門家を一つの機関に集中してレベルアップに取り組むということが、この法案に書いていない。NISCを改組するとしても、生え抜き職員がずっといるわけではなく、いろんな官庁から来て、2~3年経ったら元の官庁に帰っていく。本当の専門家集団になるような人事をどうのように行うのかという問題がある。日本の公務員の人事制度は、一つの役職の任期が短いため、専門性が低くなる。日本のキャリア官僚は、一つのポストに1~2年しかいない。このような人事をしているのは日本だけだ。私も渉外で欧米の官僚組織とも付き合ったが、1ポストは4年くらい務める例が普通である。しかも、専門性の高いポストは、(昇任しながら)十何年も同じ人がやっているケースもある。
― なぜ日本の国家公務員の人事制度は変わらないのか。
(茂田)変えようと思えば変えられるが、惰性で続けているだけだ。どの官庁も、短い任期を前提として仕事、経歴の管理が出来上がっており、異動しないと昇進が遅れたりする。東日本大震災のときに原子力発電所であれだけの大事故が起きたのに、日本の監督官庁の役人で懲戒処分を受けた人は一人もいない。このようにアカウンタビリティが全然ない。人をころころ変えるから、大事故が起きても、現職の人の責任ではないということになりかねない。過去の責任者は誰かといっても、1~2年で人が変わっていくと、その不作為が10年続いた場合、10年の間に何人もいるから、誰の不作為か分からない。大失態が発覚した時にたまたまポストのトップにいる人が辞表を出し、責任を取った形にするというのが、日本の官僚制の一般的な責任の取り方になってしまった。
関連リンク
・茂田忠良インテリジェンス研究室 – 経歴、著作、講演や発表資料など。公式サイト
・サイバー安全保障に関する取組 – サイバー対処能力強化法案及び同整備法案の概要、有識者会議の提言。内閣官房
関連記事
・政策インタビュー・能動的サイバー防御関連法案:西貝吉晃・千葉大大学院社会科学研究院教授に聞く(2025年3月19日)